| 親子でつくる木工教室 |
|
|
| 板やかく材のしゅるい |
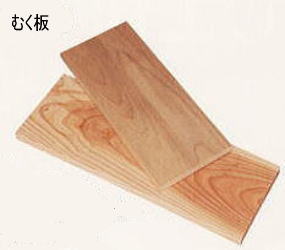 |
 |
 |
むく板
木をうすく平らにせいざい(製材)し
てあるもの。湿度によってのびちぢ
みがあるが、木の本来の美しさか
ある。
|
角材
四角くぼうじょう(棒状)にせいざい
(製材)した木材。大きな物は柱なと
につかわれる。小さな物はかこう
(加工)しやすく、そのままイスの
あしなどにしてもよい。 |
合板
うすい木の板をはリ合わせて、1枚
の板にしたもの。そりにくい。
|
 |
 |
 |
集成材
ふし(節)やわれた部分をとりのぞい
た小さな板じょう(板状)の木材を、
ならべてせっちゃく(接着)した物。
強くて長もちする。
|
ハーティクルボード
チップ状にくだいた木に接着剤を
ませてあっしゅく(圧縮)してかため
た板。 ドアのしん(芯)など、したじ
(下地)につかわれることか多い。
むく板よりのびちぢみに強い。
|
コルク板
コルクガシという木のかわ(皮)を
かこう(加工)した物。かるく(軽)
くてだんりょく(弾力)がある。
|
 |
 |
 |
やわらかい部分とかたい部分があ
るが全体にやわらかい木材。木目
はまっすくて、たてにわれやすい。
きめはあらく表面を焼いてから、
こすって木目を浮きたたせて、工作
につかうこともある。
|
白くて、きめがこまかい。ねんりん
かつまっていてへんけいしにくいの
で、ぶつぞう(仏像)やいえの材料
なとにつかわれる。あまり、木工作
にはむいていない。
|
松やにとよはれるじゅしか多い。
かたくておもく、水に強い。ねん
りんがうつくしいので、家の材料
になる。また、ハルフの原料にも
なる。
|
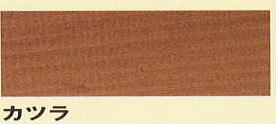 |
 |
 |
やわらく木目もうつくしい。木にね
ばりかあるのてわれにくく、加工し
やすい。かまくらほり(鎌倉彫)なと
のこうげいひんやはんが(版画)の
ざいりょうにつかわれる。
|
日本の木の中ていちばんかるく、や
わらかい_すいぶんをよくすい、ねつ
にもつよいのて、きもの(着物)をい
れるタンスや大切な物をほかん(保
管)する箱なとにつかわれる。
|
70数しゅるい(種類)におよぶ、フ
ィリピンの木材のそうしょう(総称)。
さいきんはインドネシアからのゆに
ゅうが多く、メランチとよばれている。
多くは、ベニヤ板の材料になる。
|
 |
 |
 |
シナ合板として家のざいりょう(材
料)につかわれることでゆうめい
(有名)。かわきやすく加工しやす
いので、わりばしやマッチぼうなと
にもつかわれる。
|
せかいてきにゆうめいなこうきゅう
材。イント、ビルマなとでとれる。
心材は黒またはむらさき色のしま
もようか美しい。かぐ(家具)なとに
つかわれる。
|
メキシコ南部からヘルーてとれる、
せかい一かるい木。やわらかく、
かこう(加工)しやすいので、もけ
いづくりによくりよう(利用)される。
ブイやきゅうめいようぐ(救命用具)
にもつかう。
|
| もくざいの加工 |
| いたどり(いたに線を書く) |
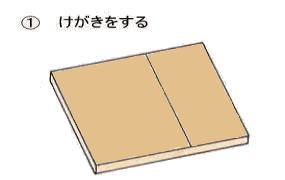 |
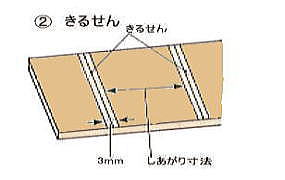 |
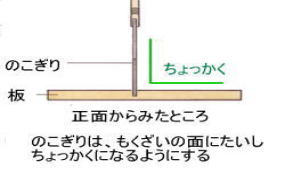 |
いたどり
けがきをする まっすぐに切るた
めには、目安となるちょくせん
(直線)をひいておく。
|
切る線
1枚の板からいくつも材料を切り出
すときは切りしろをみこんでおく。
●のこぎりの切リしろと、やすりがけ
などでけずれる分を 3mmぐらい考
えておく。しあがりの寸法
|
いたを切る
のこ身は、もくざい(木材)の面に
たいして、いつもすいちょく(垂直)
にする。
|
| いたを切る |
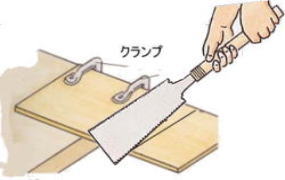 |
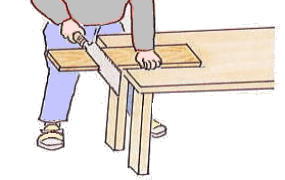 |
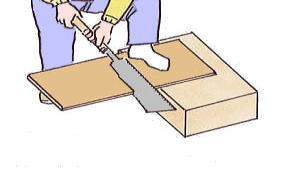 |
あてとめがついているこうさくだい
(工作台)などでは、あて木をつか
って、板をこてい(固定)する。
|
足をぜんご(前後)にひらいてしっか
りと立ち、左手で板をおさえる。
|
床に台をおいて、足で板をふんで
おさえる。
|
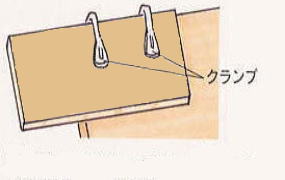 |
|
|
板の大きさによっては、万力やクランブをつかって固定してもよい。
|
|
|
| いたのきり方 |
 |
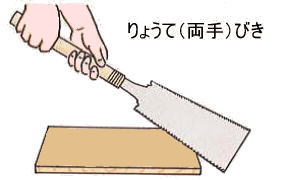 |
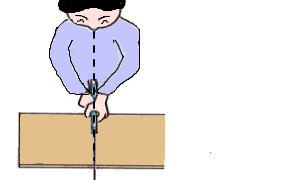 |
片手びき
柄の中ほどをしっかりにぎる。
|
りょうて(両手)びき
左手でえがしら(柄頭)を、右手で柄
じりをにぎる。(左ききの場合は逆)
|
けがき線、のこ身、目線が一直線に
なるようにする。
|
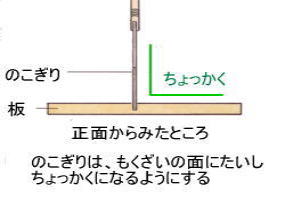 |
|
|
| 糸のこぎりのつかい方 |
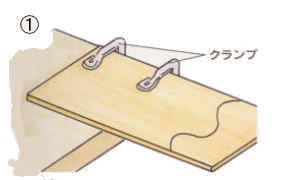 |
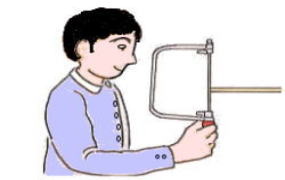 |
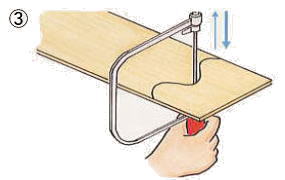 |
切る
板をクランブなとでしっかりと固定
する。
|
けがき線が見えるいち(位置)にか
まえて、刃を板にすいちょく(垂直)
にあてる。
|
ひくときは強く、もどすときはかるく
(軽く)おして、切リすすむ。
|
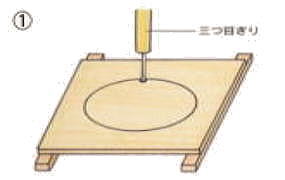 |
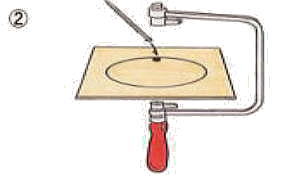 |
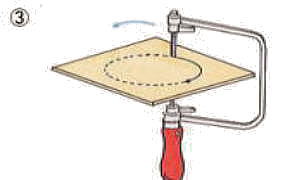 |
切りぬく
刃をとおすあなを、三つ目ぎリで
あける。
|
一度、刃をはずしてから、あなにと
おしてとめる。
|
刃がすすむ先のけがき線を見なが
ら、ゆっくり切りすすむ。 |