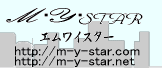
湘南の古都鎌倉 |  |
| 2026 年 01 月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| - | - | - | - | - | - | - |
|
|---|
| | 最終更新日 2026:01:01
|
湘南の天気予報 | 只今の時間 2026年01月20日(火)18時21分 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| 曽 我 物 語 |
| 曽 我 兄 弟 の 仇 討 物 語 |
|
| 曽我物語の発端 > 曽我兄弟の仇討ち > 大磯の虎・曽我物語の地理 |
仇討ちにのぞんだ十郎は21歳、五郎は19歳、父の横死さえわきまえぬ幼児が足掛け18年も仇討ちを考えていた。二人は巻狩を仇討ちの場とするに当たり、箱根権現に祈願した。
このとき箱根権現の別当・金剛院行実は十郎に太刀・微塵丸を、大願成就を激励したという。微塵九ぱ木曽義仲の愛刀であり、薄緑の太刀は義経の奉納刀だ。いわけともに頼朝には恨みを含む太刀である。後の征夷大将軍徳川宮座は勢州村正の鍛えた万を妖刀とし、徳川水を滅す刀であるとしりぞけた。宮座を恨む者が、たまたま村正鍛えの刀を持っていたからだけでなく、頼朝の故事を家康が忌み鎌ったのであろう。
平家が壇ノ浦に沈み、義経も滅び、奥州藤原氏も倒れ、後白河法皇が崩御し、建久3(1192)年、頼朝は征夷大将軍になた。
しかし、御家人は決して一枚岩ではなかった。兄弟の仇、工藤祐経は頼朝の重臣だったが、彼は比較的新しく頼朝にとりたてられていた。
東国出身だが京都での生活が長く、貴族趣味の頼朝に気に入られていた。古くから頼朝に仕えていた武人タイプの御家人たちは、祐経(すけつね)を妬んでいた。というわけで、反頼朝・反祐経勢力が曽我兄弟の仇討ちを利用して頼朝・祐経の殺害を図ったという説が登場するわけです。
仇討ちのあと、頼朝の弟、範頼が謀叛の嫌疑をかけられて伊豆に流され、古くから頼朝に仕えていた大庭景義、岡崎義実が出家します。出家とは失脚を意味する場合もありました。仇討ち後の一連のできごとが頼朝・祐経暗殺計画説の根拠になっています。
化粧坂から当時の鎌倉を考えて見よう。五郎時致(ごろうときむね)は坂上の遊女屋から小町にある工藤の館をうかがったが、警戒がきびしく襲撃きなかったという。前述のように頼朝の大蔵屋敷さえ、板塀をめぐらす程度の簡素な構えであった。御家人の館がそれほど厳重であったとは考えられない。たとえば軍力において北条氏以上の大豪族であった上総介広言さえ、鎌倉では至極かんたんに殺されている。
そこで曽我兄弟の仇討ちに仕組んだ、反北条派御家人のクーデター説が浮かんでくる。それにしては殺されもしない頼朝が″死んだ″と伝えられた手回しのよさが不可解である。仮に頼朝が反北条派に殺されたとしても、北条時政は鎌倉の動揺を押えるため、事実をできるだけ隠蔽すべきであり、それが兵法家としての″いろは″である。
頼朝は武道錬磨のため、好んで巻狩を催した。陰暦7月26日から5日間は、恒例として信州霧が蜂の旧御射山に出かけ、武士回に武技を競わせたという。しかし頼朝の武人としての評価は、義経の半分にも達していない。巻狩に事よせて浮気の場を求めたとの憶測もある。
那須野、富士の裾野、霧が峰が、獣の宝庫であったことは、想像に難くない。後年の1725年(享保10年)でさえ、徳川八代将軍・吉宗は、江戸から目と鼻の先の葛飾野(千葉県市川市付近)で巻狩を催し、猪、鹿など八百頭を仕止めている。
富士の巻狩で工藤祐経が討たれたのは5月28日の夜であった。仇討の概略をしるすと、伊豆の豪族、工藤結経は、まだ平家の家人であったころ、伊東祐親との土地争いに敗れた。二人はともに工藤定径の孫である。
頼朝が鎌倉幕府を開いた。翌年、頼朝は富士の裾野で巻狩り(大掛かりな狩)をした。この知らせを耳にした兄弟は、これこそ亡き父の仇を取る絶好の機会と思った。
将軍は、巻狩りの際、沢山の家臣を伴っていた。兄弟はその一行にもぐりこんだ。
実は、昼間も、巻狩りの間、祐経の居所は確認できたものの、いつも大勢に囲まれており、近づくことは容易ではなかった。
決行の晩、兄弟は岩陰に身を隠し、祐経の宿所に如何に近づくか相談した。しかし、近くの滝の轟音に打ち消され、お互いの声が聞きとれなかった。大切な話をしている故、しばし音を止めてくれるよう、神様、仏様に祈る思いだった。実際、二人の密談中、滝の音がしばし止んだとも言われている。
兄弟は、宿所をあちこち調べます。祐経の宿所は将軍の近くと見当をつけます。月が雲間よりしばし顔を出したので、祐経の宿所がわかります。月が雲間に隠れるとたちまち豪雨、その雨音のおかげで、祐経の寝所への侵入が容易になったのです。
この時祐経は、宿所で備前国の住人王藤内(わとうない)と、手越の少将・黄瀬川の亀鶴等の遊女を交えて酒盃を重ねていた。
祐経が兄弟によって討たれると、遊女たちは泣き叫び、大声で異変を告げた。
『吾妻鏡』には、
『「廿八日、癸巳。小雨降る。日中以降霽(は)る。子の剋(きざみ)、故伊東次郎祐親(すけちか)法師が孫子、曽我十郎祐成(すけなり)・同五郎時致(ときむね)、富士野の神野の御旅館に推参致し、工藤左衛門尉祐経(すけつね)を殺戮(さつりく)す」
「これによって諸人騒動し、子細を知らずといへども、宿侍(しゅくじ)の輩は皆ことごとく走り出づ。雷雨鼓(つづみ)を撃(う)ち、暗夜燈を失ひて、ほとほと東西に迷ふの間、祐成等がために多くもって疵を被る」』
といった状態になったと記載されている。
祐経の手が刀に届こうとした時、十郎は祐経の左肩から右わきの下にかけて切りつけた。十郎も祐経の腰に刃(やいば)を入れ、とどめを刺した。兄弟は勝利の雄叫び(おたけび)をあげた。
「我こそは、河津三郎が子、十郎祐成、同じく五郎時致なり。たった今、父の仇、祐経を討ち取ったり」
兄弟は駆けつけた部下たちと渡り合い、十郎は仁田忠常に討たれた。五郎は頼朝の御前目指して奔参したが、大友能直(よしなお)に制せられ、小舎人五郎丸に捕らえられた。
騒ぎが静まると、頼朝の命で和田義盛(よしもり)・梶原景時によって検死が行われ、死骸が工藤祐経であることが確認された。
翌日、五郎は将軍頼朝の前に引き出され、尋問を受けた。祐経は将軍頼朝の寵臣(ちょうしん)の一人であり、見事父の仇を討ったとは言え、死が待ち受けていることを五郎は重々承知していた。
『吾妻鏡』には、
『「祐経を討つ事父の尸骸(しがい)の恥を雪(すす)がんがために、ついに身の鬱憤の志を露はしをはんぬ。祐成九歳、時到七歳の年より以降(このかた)、しきりに会稽(かいけい)の存念を挿(はさ)み、片時も忘るることなし、しかうしてつひにこれを果たす。」』
と記載されている。
五郎は恐れ気もなく、工藤祐経の命(めい)を受け郎党に、父が射殺されたことを将軍に告げた。自らの18年に及ぶ艱難辛苦の日々についても語った。頼朝自身、若かりし頃、流人(るにん)として辛い日々を過ごしたことはご存知のことと思います。
頼朝のみならず同席の誰もが、親を思う子の気持ちに痛く感動した。頼朝は寛大に処理しようとしたが、祐経の遺児犬吠丸(いぬぼうまる)の、父殺害の五郎に死罪を、という嘆願により、頼朝は断首を申し渡した。
五郎が言いました、「本望なり、死は覚悟の上のこと。あの世とやらで亡き父や兄と、早く対面したし。」
十郎22歳、五郎20歳だった。
建久4年(1193年)ごろ、頼朝の周辺や鎌倉付近では、次々と事件が起こっている。まず富士の裾野で催された大がかりな巻狩りの際、曽我兄弟が父の敵の工藤祐経を討ち取った。曽我の敵討ちとして有名だが、実は殺された、工藤祐経は頼朝の寵臣であり、その人を討つということは、頼朝を中心とする東国の武家秩序に対する反逆であった。
従って仇討ち成就は死を覚悟しての行動であった。『吾妻鏡』が、五郎が頼朝の面前で心底を述べ、成就の暁には自害するつもりであったと、記していることはそのことを意味している。
鎌倉に仇討ちの事件が正式に知らされたのは5月30日であった。だが頼朝の死の聯は29日の未明には、化粧坂を下って鎌倉中にひろまりつつあった。このとき源範頼は巻狩に加わらず、鎌倉で留守をつとめていた。
鎌倉の留守をあずかった彼は、頼朝の死が真実なら、よほどしっかりしなければなるまいと自分を励まし、頼朝の安否を心配する妻政子に対して、源範頼が「範頼が控えておりますので(ご安心ください)。」と見舞いの言葉を送り、政子を慰めたのである。この一言が範頼の命取りになった。
源範頼の謀叛人扱いは、頼朝が鎌倉に帰館するなりのことであった。範頼は狐につままれた思いでキョトンとした。そして頼朝の疑いをはらそうと、浜の館に謹慎して、必死に起請文の筆を執った。その範頼に風のような声がきこえた。
「三河殿、御命危うし、御命危うし」
範頼の背筋を寒いものが走った。確かに腰越・清福寺でしたためた源義経の起請文は反古にひとしかった。範頼は義経の運命が、自分の身にかかりつつあることをおぼろに感じとっていた。謀反の疑いと取られ範頼は伊豆修善寺に幽閉され、そこで殺される。
曽我兄弟のあだ討ちからわずか二ヶ月しか経っていない。
武士の亀鑑と、長年はやされてきた曽我兄弟の仇討には、腑に落ちない点が多い。仇討ち騒ぎが蒲冠者範頼の死へとつながること。また曽我兄弟が工藤祐経を討ち取ったあと、頼朝の寝所にまで侵入したとの情報、つづいて御所様御落命の噂が、鎌倉にいち早く流れたことなどである。
仇討ちを成就しながら横死を遂げた兄弟の霊は、その思いを霊媒として巫女に語らせるというところから、その伝承が始まったという。
そしてこの曽我兄弟の仇討ちの口承者は、箱根山とかかわりをもつ修験比丘尼であったという指摘がある。
中世、箱根山は、死者たちの霊魂がさまよう山といわれていた。弘安3年(1280)この山を越えた歌人飛鳥井雅有(あすかいまさあり)は、「この山にぢごくとかやありて、死人つねにゆきあひて、故郷へことづけするよしあまたしるせり。いかなる事にか、いとふしぎなり。」(『春の深山路』)
と記している。死者たちの霊魂は国境に集まる。箱根山は、東国と西国の境の山であった。
横死した兄弟の霊が、さまざまの災厄や虫害をなすという民間伝承が東国の各地に伝わっている。
小田原市には、曽我兄弟のお墓がある「城前寺」、また富士宮市には、音を止めた「音止めの滝」、兄弟が身を隠したという「隠れ岩」が、この滝の近くにあるなど、曽我兄弟にまつわる場所が多々あります。
小田原市曽我谷津城前寺では、毎年兄弟が討入りした5月28日に傘焼きが行われる。各家庭で使い古した唐傘を集め、無事息災、至福繁昌を祈って焚きあげる行事である。この行事がいつ頃から行われていたか定かではないが、江戸後期にはすでに行われていたという。江戸時代には傘がカサ(病根)にも通じる意味もあって悪疫退散を祈っての行事であろうが、関東の御霊信仰と結びついた伝統行事と思われる。 |
日本三大仇討ちの一つ、曽我物語の曽我十郎・五郎兄弟が父の仇を討つ際に、傘を燃やして松明にしたという故事にちなみ、十郎・五郎に扮した幼児が全国から奉納された古傘に火をつけて燃やし、兄弟の霊を慰めます。
場 所 :曽我の里 城前寺(小田原市曽我谷津592)
交通 :JR御殿場線下曽我駅徒歩10分 |
| 曽我兄弟の菩提寺 |
| 曽我の城前寺 |
城前寺境内 |
 |
 |
| 小田原曽我にある城前寺(じょうぜんじ)は曽我兄弟の菩提寺十郎・五郎の兄弟のほか、継父祐信、母満江供養墓 |
 |
 |
| 傘焼き行事 |
 |
 |
|
|
| 曽我物語の発端 > 曽我兄弟の仇討ち > 大磯の虎・曽我物語の地理 |
|
|
|



 |